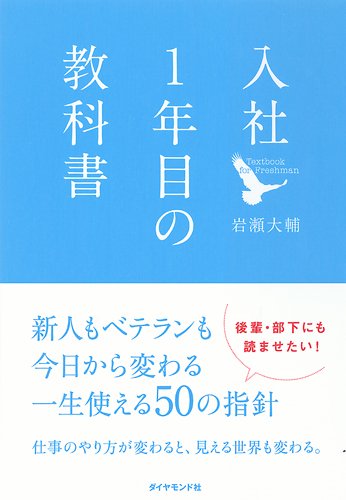
こんな人におすすめ
- 入社1年目の人
- 新卒1年目の人
- 仕事に行き詰っている人
- 仕事のやり方を見直したい人
タイトル通り、新卒1年目の人、転職して入社1年目の人は絶対読むべきです。
しかし、仕事に慣れてきた中堅社員の方や、ベテランの方にもおすすめできる内容でした。
その理由は、本の構成にあります。
構成は以下の通り
- はじめに「仕事において大切な3つの原則」
- コラム1 会社選びの3つの基準
- コラム2 70歳になっても勉強し続ける意味
- コラム3 キャリアアップは人磨き
- コラム4 チャンスをつかめる人になれ
- おわりに 社会人の「勝負所」は最初の瞬間
- 巻末 僕がおすすめする本
- 巻末 僕がチェックするTwitter
全体的新卒1年目向けに書かれていて、仕事の基本中の基本なことが書かれています。
しかし、この基本中の基本を完璧にマスターしている人はいるのでしょうか??
例えば、、、
- メールの返信
- メモの取り方
- 議事録の取り方
- 会議の発言
- 社員との距離感
- 上司とのコミュニケーションetc
これらを、すべてマスターしている人は少ないのではないでしょうか???
ベテランの方でも、一度原点に返ることの大切さを教えてくれる本です。
仕事の基礎~キャリアアップまでの道のりが書かれています。
社会人としての人間性、仕事人としての人間性を高めるための内容でした。
特に気になった点に焦点をあてながら解説していきます。
仕事の3大原則
さっそく冒頭に以下の3点があげられました。
- 頼まれたことは、必ずやりきる
- 50点で構わないから早く出せ
- つまらない仕事はない
この3点が筆者が伝えたいことだと思います。
頼まれたことは、必ずやりきる
著者が社会人になって最初に、同室になった先輩にこう言われたそうです。
「岩瀬、新人のうちは頭がいいとか優秀だとかというのは、どうでもいいことなんだよ。上に頼まれた仕事を何が何でもやりきってくれるか。仕事を頼む側からすると、最も大事なことは、そういうことなんだよ」
頼まれたことは、どんなに小さいことでもやりきる。
督促される前にやりきる。
一人でやりきれないものでも、上司に報告をしながら前に進めばいい。
どんなことがあってもやり切る人に、次の仕事が回ってくるのです。
周囲から信頼に足る人だと評価されれば、次の仕事が回ってきます。
そうすることで、量が増え、経験値が増え、質も上がってくるのです。
頼み事をやりきる→仕事が回ってくる→量が増えることで質もあがる
こうすることで、他の人との差が広がっていくのです。
と著者は述べています。
50点で構わないから早く出せ

1か月で100点を目指すより、50点を1週間で目指す方がいい。
仕事に慣れていない新人が、100点なんて簡単にとれません。
50点の仕事に赤ペンを入れてもらい、アップグレードすればよいのです。
そうすることで、1か月もせずに100点を目指せるのです。
仕事に求められるのは、、
- 成果を出すこと
- スピード(期限を守ること)
仕事は、学校の試験とは違います。
仕事は総力戦です。
ある程度、自分のできることを調べて、50点でいいから提出する。
それが新人に求められる能力なのです。
つまらない仕事はない
著者に言わせれば「つまらない仕事などない」そうです。
単調な仕事でも、面白くする方法はいくらでもあるとのこと。
目的や用途を考えれば、様々な工夫ができるとのこと。
さらに、疑問点、改善策、提言、質問事項など、、、
つまらない仕事こそ、じぶんなりの付加価値をつけることに意味があるのです。
新人向け(仕事の基礎)
何があっても遅刻するな
入社1年目の社員に対して、周りの社員は、、
「社会人としての当たり前のこと、ちゃんとやれる人物か」
という色眼鏡で見られています。
入社1年目の職員に、成果は求められていません。
むしろ仕事を教えてもらう立場にあります。
だからこそ、当たり前のことを当たり前にこなすことが重要なのです。
たった1回の遅刻でチャンスを逃し、能力を発揮する場面を奪われることもあるのです。
メールは24時間以内に返信せよ

メールの返信は、
- 対応が速いだけで2割増の評価を得られる。
- 結論を先に述べ、詳しいに内容は後述する。
私自身も、メールの返信を後回しにしちゃいます。(笑)
むしろほとんどの人がそうなのではないでしょうか??
みんなが後回しにしがちだからこそ、即レスするだけで高評価が得られる。
いい意味で目立つことができますね!!!
メールを受け取った側からすれば、この人と仕事がしたいと思ってくれるはずです。
また、自分より役職が上の人は、自分の2~3倍のメールがたまっています。
それゆえ結論ファーストが重要なのです。
なんのためにで世界が変わる
仕事の優先順位をつける上では、、
- 締切日
- 何のためなのか?
締切日が一番大切なのは、言うまでもないでしょう。
+αで「何のためですか??」
これを聞ける人物は、仕事ができる人だそうです。
前提条件や知識があれば仕事の取り組み方も変わってきます。
それゆえ「何のためですか?」は重要なのです。
※注意※ いきなり「何のためですか?」と聞くのはNG。
生意気、消極的だと思われる。
いったんは、

わかりました!!
と答え、その後に

それは何のために使うのですか?

もちろんやります。でも、お聴きしたほうが良い仕事ができると思いますので、差し支えなければ、何のために使うか教えてください。
とクッション言葉が大切です。
単純作業こそ「仕組化」「ゲーム化」

新人の頃は、単純な作業がほとんどでしょう。
先ほど述べた通り、つまらない仕事なんてありません。
例えば資料の作成やまとめです。
どんな仕事にも、あなたならではの付加価値がつけられるのです。
頼まれていないことも+αでできる人間は差別化にもつながります。
自主的に工夫し、提案し、実行し続ければ、
そのクリエイティブさが評価され、次に依頼される仕事は単調なものではなくなるはずです。
仕事は復習がすべて
みなさん、仕事でメモしたものはいつ見返していますか???
仕事中??家に帰ってから??
意外とメモをとって終わってしまう方がほとんどではないでしょうか??
著者は、移動中の車内で見返しているそうです。
これは非常に効果的だなと思いました。
移動中の車内って、やることがないですよね。
電車の中では、個人情報の記載されたメモは見れません。
かといって、家に帰って仕事の復習をするはおきないでしょう。
移動中の車内は絶好のチャンス。
気づきや学び、覚えたこと学んだことを定着する時間を、つくることが大切です。
会議の参加方法
会議では新人でも必ず発言せよ

会議に参加したら、、、
何らかの形で貢献するのが社会人のルール
となります。
お客様気分でいることはルーキーでも許されないのです。
では分析力、問題解決能力に乏しいルーキーがどのように貢献すればよいのでしょうか??
それは、、
- 新鮮な目線
- 現場の感覚を伝えること
経験のあるベテランは、、
蓄積した経験値をもとに、目の前の問題に対処します。
その反面、思い込みに陥ることもあります。
そんなときに、思い込みのない素直な視線が必要なのです。
その意見が思わぬ解決策につながることがあります。
これこそがルーキーにできる付加価値のつけ方のなのです。
もう一つは、自分で現場に足を運んだ際に得た顧客の意見を伝えることです。
管理職や上司になるにつれて、現場に足を運ぶ機会が減ります。
過去の現場の記憶で判断しがちです。
そこで、最新の情報をもつルーキーの現場で得た声が求められるのです。
「あえて言わせてください」で意見を言え
上記のように会議は、参加した以上、発言する義務があります。
しかし何もしらない新人にとって、、

こんな幼稚なこと言って叱られないだろうか??
など遠慮や緊張など不安でいっぱいでしょう。
発言する際は以下のように言うとよいでしょう。

私はまだ素人かもしれませんが、あえて素人目線で申し上げます。

もしかしたら役に立つかもしれませんので、聞いていただけませんか?

皆さんの意見のこういう点はとても参考になります。私も賛成です。ただ一つ疑問に感じたことがありますので、ちょっと筋違いなことかもしれませんが、あえてこういわせてください。
- 相手への敬意を払う
- 相手の意見を踏まえてから話す
- 上から目線で話さない
この最低限のルールを抑えればいいのです。
実は上司や先輩にはルーキーの意見を聞いてあげたいという親心のような気持ちを持っているのです。
むしろ、参加する姿勢を見せることで、多少粗削りでも、
議論に貢献しようという姿から、仲間意識が芽生え、次のチャンスが巡ってくるのです。
若さは特権です!!
最低限のルールを守り、積極的に発言する若手こそ可愛がれ、チャンスが巡ってきます。
自己研鑽
目の前だけではなく、全体像を見て、つなげよ
仕事をしていると、、

今自分がやっている仕事ってなんのためなんだろう。。。。
って思うときってありませんか???
仕事って全体像が見えてこないと、目の前のタスクの目的や意味がわかりませんよね。
ゆえに、作業効率が落ちてしまいます。
そんなときこそ、
自分の会社の財務諸表をみるべきなのです。
自分の会社は、どこからお金を調達し、どのように投資され、どんな形で返ってくるかを考えましょう!!
そこから自分が手掛けている業務がどのような形で企業価値の向上につながっているのか、考えるのです。
いわばマクロの視点が身についてくるのです。
営業マンは明日のことを考えます。
部長は1か月後のことを考えます。
社長は1年後のことを考えます。
財務諸表を意識し、マクロの視点とミクロの視点から考えると、
自然と社長目線、経営者目線で仕事に取り組めます。
ビジネスマンとしての力量が身につくのです。
人間関係
仕事に関係ない人とランチせよ
こんな人とランチに行け!!
- 自分とまったく関係ない部署の人
- 他業種や他社の人
- 社長(可能であれば)
上司は部下とランチに行きたいと思っているのことがほとんど。
昨今、ハラスメントが流行し、上司はかなり気を使っています。
複数名で誘えば、気まずい雰囲気にもなりません。
ランチでいろんな人の話を聞き、見聞を広めることが大切です。
相手との距離感を誤るな
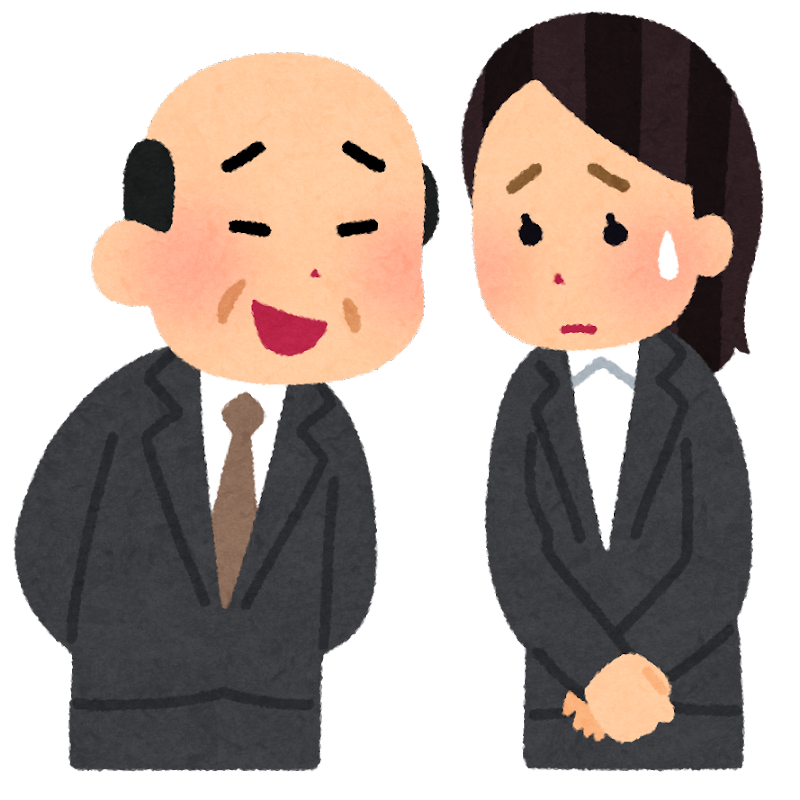
中途入社が増え、雇用形態が多様化している昨今は、立場と年齢が逆転するケースが増えています。
この状況でも著者は、
年齢が上の人には、無条件で敬意を払うようにしているそうです。
逆にそれは、年下の人にも同様です。
著者が学生向け講演会で仲良くなった学生と飲みにいきました。
その後学生から、お礼のメールが届きました。

岩瀬さん、昨日はありがとうございました。また飲みに連れていってくだいさい!
対して著者は、

○○さま、昨日はありがとうございました。
はたから見るとよそよそしいかもしれません。
しかし、仕事上のつきあいでは一定の距離感をもって接することが望ましいとされています。
ここは、すごい納得しました。
昨今、セクハラなど問題視されています。
セクハラが起こるのは上司側が距離感を誤るがゆえに生じてしまうのです。
仕事上の上司と部下の関係性が保たれていたとしても、
それはあくまでも仕事上の関係性。
それを仲良くなったと勘違いしてしまうから、
ハラスメントが起きてしまいます。
仕事をしているときは、一定の距離感をとっておく。
このくらいの距離感がちょうどいいのかもしれません。
悩みは関係のない人に相談

入社して最初のうちは、仕事を覚えるのに必死で悩みもないでしょう。
しかし数年たつと、仕事や人間関係などに悩みが生まれてきます。
たいていは、上司に言えず、同期に話すことになるでしょう。
しかし、解決には至らず、話を聴いてもらって終わってしまいます。
そこで、筆者は、
利害関係のない人、自分とは目線や立場、考え方の異なる人に相談することをすすめています。
例えば、、
- 他社の先輩
- 両親
この人たちは、意外な観点からアドバイスしてくれるかもしれません。
キーポイントは、
社外、年上、目線の違う人です。
同期とはつき合うな
この部分を読んで、驚きました。
著者が同期と付き合うべきではない理由は以下の2点です。
- 同期同士で比べてしまう
- 思考が内向き化してしまう
同期は支えにも刺激にもなる存在です。
しかし数年後、会社での立ち位置が明確化されてしまいます。
「あいつの方が上司に気に入られている」
「あいつの方がボーナスが10万円高かった。」
人は、人と比べている限り幸せにはならない。
優越感に浸っても所詮井の中の蛙です。
会社の同期と飲みにいっても、会社や上司のゴシップで終わってしまいます。
会社の人とばかりつるむと、スキルや思考がその会社でしか通用しないものになってしまいます。
こうして視線が外へ向かなくなってしまいます。
井の中の蛙にならないように、会社の外の人間と交流するのことが大切だと述べています。
まとめ&感想
- 入社1年目は、マイナス評価を受けない事が大切
- 仕事はチームで結果を出すもの。50点でいいから次に回す
- 仕事は付加価値をつくりだすことを求められる
- 社内より社外とのコミュニケーションが大切
著者の言いたいことはだいたいこんな感じだと思います。
タイトルは「入社1年目の教科書」とあり、新卒向けの内容かなーと思いましたが、
内容は、新卒、中堅、ベテランにも役立つ内容でした。
新卒なら、この本で読んだことをインプットし実際にやってみる。
中堅、ベテランは仕事の取り組み方を、振り返る機会になる内容です。
イメージとしては、
新卒向けの内容8:中堅、ベテランにも使える知識2
といった内容でした。
新卒や大学生にはぜひおすすめです。
仕事の取り組み方がわからなくなっている。
初心に立ち返りたい。
という思いがあるなら、
中堅やベテランにもおすすめできるかなーっていう感じです。
この記事が「入社1年目の教科書」の購入に役立てば幸いです。
それでは(@^^)/~~~


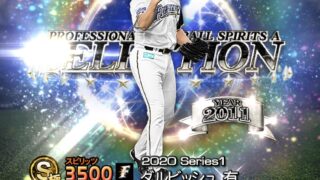



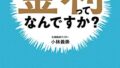
コメント