SFF、ツーシーム、亜大ツーシーム、パワーカーブetc
時代が進むとともに、新しい変化球が増えてきます。
最近では、「スラッター」という球種も聞くようになりました。
この記事はこんな人におすすめです
- スラッターのことを全く知らない人
- スラッターの起源を知りたい人
- スラッターの投げ方を知りたい人
- スラッターの変化を知りたい人
それではさっそくやっていきましょう!!!
本格的にスラッターの
スラッターの起源
自分が記憶している限りでは、2017年頃、則本昂大投手が、

スライダーとカットボールの中間級として投げる
とメディアに話したことが最初ではないかと思います。
(あくまでも私の曖昧な記憶です)
しかし、以前からこのボールの存在に気づいている人がいました。
そうかの有名なお股ニキです。
起源は非常にあいまいです。
お股ニキが言うには、2015年ごろメジャーリーグのジェイク・アリエッタがこのボールを投げたあたりが始まりではないかと推測されています。
アメリカでのトレンドは、日本に数年後遅れてやってきます。
(カットボール、ツーシーム、フライボール革命、シフト、ノーテンダーなど)
これに気づいたお股ニキが、日本で火付け役になったのは間違いありません。
本格的にスラッター、お股ニキのことを知りたい人は、お股ニキの著書がおすすめです。
スラッターだけではなく、現在の野球界のトレンドについても解説しています。
スラッターまでの歴史と変遷

ではなぜこのボールが広まったのでしょうか??
それはおそらくフライボール革命による影響が大きいと考えます。
しかし、スラッターを理解するには、10年ほどMLBの歴史を理解しなくてはなりません。
メジャーリーグでは、年間約160試合、投手は中4日でローテーションを守らなければなりませんでした。
そのため、1試合あたり100球程度、交代となります。
つまり、球数が増えてしまうと、イニングが稼げません。
球数を増やさずに、打者をどう打ち取るか?
これが、投手に課せられた大きな課題でした。
その解決策として、主流となったボールが、、
ツーシームとカットボールなのです。
これらは以下の特徴があります。
- ストレートに近いスピードで手元でボール1~2個動く
- ストライクゾーンで勝負できる
- バットの芯を外す球
球数を増やさずに、簡単にアウトのとれるボールがこうして流行しました。
さらに、MLBでは極端な守備シフトが流行します。
打者の打球方向を徹底的に分析して、極端な守備位置をとる作戦が基本となりました。
従来のポジションなら、ヒット性だったあたりがアウトになる。
打者は、この2つの策に手を焼いていました。
この作戦に打者も黙っていません。
極端なシフトに手元で動くツーシームとカットボール。
この2つに手を焼いていたバッター陣は、こう考えました。

狭いヒットゾーンの中でヒットを打つより、一発で仕留めてホームランにしてしまえばいい。
この作戦に対抗するため、生まれたのがフライボール革命です。
この時期には、セイバーメトリクスを中心に野球をデータ分析することがMLBでは主流でした。
打球を種類別でみてみると、意外なデータが判明しました。
- 長打確率は、フライ、ライナー>ゴロ
- 安打は、フライ>ゴロ
これは驚きですね。
長打を打つには、フライやライナーを打つ。
これは、イメージ通り納得できます。
しかし、単打を含めたヒットになる確率は、フライの方が高いのです。
MLBでは、シフトの普及によって、ゴロで野手の間を抜くことが極めて難しくなったのです。
さらにバレルという指標が普及しどんな角度でバットを出し、スイングスピードがどのくらいあれば、飛距離が伸びるのかが解明されました。
19度のアッパースイングでボールの中心から0.6センチ下をインパクトすれば、飛距離が最大化します。
それゆえ、アッパースイングが効果的となりました。
ツーシームやカットボールは、ストレートより落ちる軌道となります。
ゆえに、これらのボールはフライボール革命の餌食となりました。
そこで、ピッチャー陣はさらに考えました。
アッパースイング気味の打者にフライボール革命。
これらに対抗するには、バットに当てさせないボールが必要です。
アッパースイングに当てさせないために、
ホップ成分の高いストレート。
ストレートに偽装するピッチントンネルを通過するボール。
こうしてスラッターが生まれたのです。
このバッターとピッチャーのイタチごっこの末、生まれたボールがスラッターなのです。
スラッターの変化
- カットボールのように鋭く、スライダーのように曲がる
- 横の変化量はカットボール
- 縦の変化量はスライダー
- 縦のカットボールに近いイメージ
- ジャイロ回転
このような特徴を持っています。
イメージ的に、カットボールのスピード感と鋭さで、カットボールより縦に曲がる、イメージでしょうか?
え?それって高速スライダーや縦スライダーじゃないの?
これらと大きな違いは、ジャイロスピンです。
高速スライダーは、サイドスピンが強く、軌道が「ふわっと」した丸み帯びた軌道になります。
スラッターはストレートの軌道に近いところから「かくっと」鋭角気味に曲がります。
いわゆるピッチトンネルを通過するので、ギリギリまで球種の判別が難しいのです。
スラッターのメリットデメリット

メリット
- ストレートと似たようなリリースや手首の角度投げられる
- 軌道やスピードもストレートに近づけやすい
- ギリギリまで判別がつかない
- 回転軸を下に向けたら、スラッターの投げ方でシュートする(いわゆる抜けスラット)
良いバッタ―は、ボールを手元まで引きつけることができます。
しかし、スラッターは手元で引きつけても判別ができません。
ゆえに万能変化球なのです。
このボールのすごいとところは、抜け球になっても武器になるところです。
(SFFも万能変化球ですがすっぽ抜けたらホームランボールです。)
リリースの瞬間はスライダー系の軌道なのに、思ったほど曲がらない。むしろシュートしてくる。
この想像とのギャップに打者は面食らうのです。
2015年くらいに山田哲人選手が、

唐川投手の抜けカットは打てない
と言っていたのはこのような理由です。
デメリット
- 動きが悪ければただの「曲がらないスライダー」
- 緩急がないため、粘られてしまう
- ストレートの質が悪くなる可能性あり
スラッターは、スピードとキレが命です。
すこしでも質が悪いと、打ちゴロのスライダーになってしまいます。
先発投手の場合、複数回同じ打者と対戦するため、投球の幅がありません。
ストレートと同じスピード感で、変化量もそこまでないからです。
しかもジャイロスピンを意識するため、小指からリリースする癖が身についてしまいます。
そうすることで、ストレートにキレやホップ成分がなくなるリスクもあります。
どんな球種でも一長一短ということですね。
どうやって投げるの?
お股ニキとも交流のあるクーニンのエース・前沢くんが解説しております。
ポイントは以下の通り
- 握りはカットボールとほぼ同じ
- カットボールの握りで、ストレートのリリースをする
- ジャイロ回転をかけにいってはいけない
このボールのキーポイントは、ストレートに偽装させること。
それゆえ、ジャイロ回転をひねってかけようとしてはいけない。
ボールの軌道がふくらんでしまうためです。
筆者もスラッターを投げてみました。
しかし、意図的に投げることはできませんでした。
どうしてもカットボールになってしまいます。
カットボールを縦気味に落とすイメージで投げるとたまにスラットすることがあります。
あくまでもちょっとしたイメージの違いなんでしょうか??
スラッターを投げてやる!!!
と意気込んで投げるよりも、
カットボールを縦に鋭く落とすにはどうしたらいいのかな?
そのための回転は?リリースは?握りは?
と自分なりに解釈していくことが大切だと思いました。
スラッターまとめ
スラッターまとめです。
- 横の変化量はカットボール、縦の変化量はスライダー
- 一言で言うなら縦のカットボール
- スライダーとの違いはジャイロ回転
- フライボール革命の対抗手段として生まれたボール
もう変化球は出尽くした。
こういわれることもありました。
しかしこうして新しい変化球が誕生したのも事実。
バッターの進化が、投手の進化を生む。
逆もまたしかり。
これこそが野球の醍醐味なのかもしれませんね!!!!
もっとスラッターについて知りたい人には、お股ニキの著書がおすすめです。
令和時代を生き抜くための投手の条件について書かれています。
ピッチングに特化した本なので、投手はぜひ読んでほしいです。
この記事がスラッターの理解に役立てばうれしいです。
それでは(@^^)/~~~


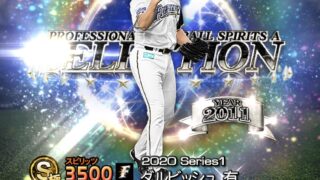



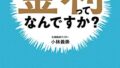

コメント