「このピンチを切り抜ければ流れが来ますね。」
野球を観ているとこのフレーズを一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか?
ピンチの後にはチャンスともよく言いますね。
野球において「流れ」はよく使われますが、その正体は非常にあいまいな認識となっています。
近年は、統計学など野球はかなりレベルの高い分析がされています。
そのため「流れ」は非科学的だ。という意見もあると思います。
しかし、15年間野球を経験してきた私から言わせてもらうと、野球において「流れ」は存在します。
では「流れ」の正体は一体どのようなものでしょうか?
私自身の経験から結論を述べさせてもらいます。
野球における流れの正体は○○
それでは、さっそく結論から述べていきます。
「流れ」の正体は、観客やアルプス含め球場の観衆である。
最小単位で言うならば、ベンチの雰囲気。
これが15年間野球を続け、10年以上プロ野球を観てきた私がたどり着いた「流れ」の答えです。
私自身この結論にたどり着いた、試合があります。
それは高校最後の夏の大会です。
私は、大舞台で野球をやる機会が少なかったので、ギャラリーがたくさん来る試合での経験はありませんでした。
そのため、プロ野球選手がよく言う、「観客の皆様の声援が力になりました。」
という発言はきれいごとにすぎないと思っていました。(笑)
高校最後の試合は、想像を超える同級生や学校関係者が来てくれ、1回戦でまさかのほぼ満員状態でした。
その環境でプレーをして感じたことがあります。
野球をプレーするのは人間である。
心をコントロールできなければ、身体はコントロールはできない。
ベストなプレーをするのは、心のコントロールが必須である。
応援してくれる人がたくさんいると当然テンションは上がり、前向きな精神状態でプレーができる。
投手は押せ押せな気持ちで腕が振れ、打者は集中力が増し、ミスショットが減る。
対して、相手チームのファンが多い場合、自分がけなされているわけではないが、なぜか自分が悪者のような感じがする。
四面楚歌のような後ろ向きな気持ち、テンションが下がる。
ミスをしたらやばいという雰囲気が蔓延する。
そのような精神状態でプレーすると、身体がこわばり、うまくコントロールができなくなる。
投手はコントロールが乱れたり、野手はエラーが増える。
というように、野球をプレーするのは人間であるため、精神的要素は大きいです。
この試合を通じて、観衆の声援はプレーする選手に大きな影響を与えることを実感しました。
相手チームの観客の声援というのは、自分たちにはどうすることもできません。
つまり、観客を味方につけることは、試合を支配することにもつながるのです。
(甲子園で逆転が多い理由、サッカーのホームとアウェイの差はここにあると思います。)
流れを感じた試合その1
野球を観てきて、流れを感じた試合があります。
それは現・中日ドラゴンズ藤嶋選手率いる東邦高校が、八戸学院光星を9回にひっくり返した試合です。
八戸学院光星の選手が試合後に「球場全体が敵に見えた」とインタビューで述べたことが鮮明に記憶に残っています。
(確かこの試合でタオル回しが禁止になったような)
球場全体が東邦を応援し、逆転を期待しています。
八戸学院光星の選手は、決して悪いことをしていません。
東邦の逆転を期待する人が増え、八戸学院光星の選手がなぜか悪者、敵かのような雰囲気になっています。
甲子園の特徴として、(アルプス以外の観衆は)ひたむきなプレーや負けているチームを応援する、贔屓の学校がない観客がたくさん来場する特徴があります。
そのため、観客が時には味方、時には敵にもなりうるのです。
精神がまだまだ未熟な高校生にとっては、初めての経験であるため、動揺につながったり、実力以上の潜在能力を発揮することもあるでしょう。
そのため甲子園は逆転試合が多く、「甲子園には魔物がいる」といわれる要因でしょう。
流れを感じた試合その2
2つ目の試合は、2015年夏の甲子園決勝 東海大相模vs仙台育英の試合です。
現・中日小笠原慎之介選手率いる東海大相模が優勝した試合ですが、とってはとられのシーソーゲームでした。
序盤は東海大相模がゲームの主導権を握っていきます。
しかし中盤6回、小笠原選手を攻めてたて、二死満塁まで仙台育英がチャンスをつくります。
アルプスが、育英名物タオル回しを始めて逆転を期待します。
するとなんと、そのタオル回しがバックネット裏、外野スタンドまで広がり、相模のアルプス以外、タオル回しが広がっていきます!!
これは球場全体が仙台育英の逆転を期待しているのです!!
(負けているチームを応援するギャラリーが多い甲子園の特徴といえるでしょう)
カウント2-1と追い込んだ小笠原選手ですが、最終的には外を狙ったボールが真ん中に入り、仙台育英が追いつきました。
ゲーム展開が東海大相模ペースでしたが、ここで仙台育英が試合の流れを呼び戻しました。
簡単に追い込み、投手有利なカウントにも関わらず、失投をしてしまった小笠原選手。
このようにドラフト一位クラスの選手ですら、流れには逆らえないのです。
「流れ」の最小単位:ベンチの雰囲気
じゃあ観客が入場しない、草野球や少年、中学野球は「流れ」なんてないじゃん!!
という結論になってしまいますよね。
当然アマチュア野球にも流れは存在します。
その構成要素はベンチの雰囲気だと考えます。
先ほど、野球をプレーするのは人間。
そのため、身体をコントロールするには、心のコントロールが必要と述べました。
では、10-0で負けている試合のベンチの雰囲気、監督が不機嫌な試合のベンチの雰囲気(高校の時はしょっちゅうでした(笑))プレーするとなると、どうでしょうか?
気持ちは後ろ向きですし、「ミスしたら怒られる」というプレッシャーから満足なプレーはできませんよね。
対して、絶体絶命のピンチを抑えた直後、スタメン選手ベストプレーをし、控え選手もベンチワークをこなし、同じ方向を向いている雰囲気ではどうでしょうか?
当然後者は、勝利に向かって前向きな気持ち、精神の安定につながっているのでベストパフォーマンスにつながるでしょう。
やることをやっているチームはベンチが明るく、控え、スタメン問わず同じ方向を向いているため、チャンスをつかめ有利な展開で試合を支配していけるでしょう。
(余談ですが、普段打てないムードメーカーの子が代打で打つと異様な盛り上がりを見せますよね。そのようなキャラを持つムードメーカーの子は、暗い雰囲気や流れを変えてくれるので、実力が劣っていてもベンチに置く価値があると考えます。)
このように、ベンチの雰囲気が明るいと精神の安定につながります。
また、たとえ負けていても、ベンチの雰囲気が明るければ、相手チームに不信感を与えることができます。
先ほど述べた、上記の2試合のように勝っているのに悪者、適役の雰囲気を与え、精神の動揺、不安定さにつながります。
こうして球場の異様な雰囲気を感じ取り、失投や、ミスショットが起こり、試合の流れが変わっていくのです。
(このような状況に陥った際は、悪役になり切りましょう。意図的にタイムをとり水を差し、相手のペースを止めることが有効です。)

流れの正体まとめ
流れの正体は、観客である。最小単位で言うならばベンチである。
と結論づけました。
味方に与える「流れ」の影響
観客が味方、ベンチワークが明るい
↓
精神の安定。前向きな気持ち。
↓
心のコントロールは身体のコントロールにつながる。
↓
ベストピッチが増え、ミスショットが減る。
相手に与える「流れ」の影響
相手に悪役のイメージを植え付けさせ、ミスしたらやばい雰囲気を与える。
↓
精神が不安定になり、身体のコントロールが効かなくなる。
↓
コントロールの乱れ、守備の乱れ、ミスショットが増える。
セイバーメトリクスの浸透により精神論は時代遅れと揶揄される時代となりました。
しかし、野球をプレーするのは機械ではなく、人間です。
観客や観衆は、プレーヤーに精神的に力を与え、時には毒をも与えるのです。
心が安定すると、身体のコントロールへつながりベストパフォーマンスへとつながります!!
このように「流れ」とは球場の観衆やベンチがつくり出す雰囲気といえるでしょう。
いかかだったでしょうか。
「流れ」についてコメントでご意見お待ちしております。
それでは。。


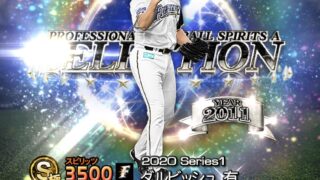

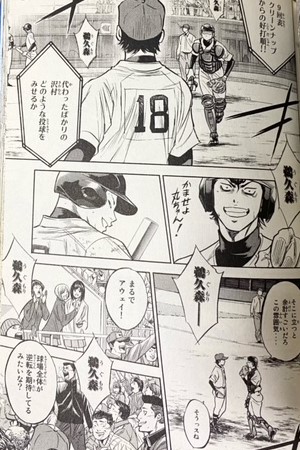


コメント