夏の甲子園がいよいよ終わりました。
仙台育英高校おめでとうございます!
今大会も様々なドラマがありました。
春夏秋制覇を目指した大阪桐蔭が敗北。
智弁和歌山が初戦敗退。
これこそ一発勝負の怖さでもあります。
ではなぜ、高校野球はこういった大番狂わせや9回裏の逆転劇が多いのでしょうか?
巷では、
「甲子園には魔物がいる」
とも言われています。
この甲子園の魔物とはいったいなんなのか?
その正体を解説していきたいと思います。
↓この記事はこんな人におすすめ↓
- 甲子園の魔物の正体を知りたい人
- 甲子園で逆転劇が多い理由を知りたい人
↓その前にこの記事を読めばより理解が深まります↓
すべてはあの大観衆が原因

甲子園の魔物の正体は、、
あの大観衆です。
甲子園となると、全国から高校野球ファンが集まります。
時に、5万人近くの観衆が集うこともあるでしょう。
5万人となると、
溜息や歓声、観客の声援や声、鳴り物が選手に届きます。
「砂の栄冠」では、この独特な雰囲気を「宇宙空間」と呼んでいます。

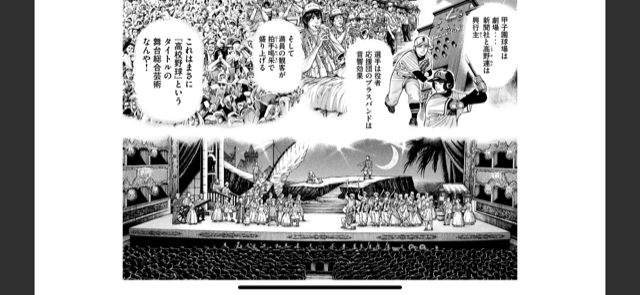

どんなに技術的に立派な高校球児でも、あの大観衆でプレーする機会はほとんどありません。
あの独特で異様な雰囲気が、
選手に精神的プレッシャーを与え、身体の自由とコントロールを奪うのです。
ボールが真ん中に集まりだしたり、コントロールを乱したり、思いもしないエラーをしたり。
そういった精神的プレッシャーをあの大観衆が作りだしているのです。
あの大観衆の声援が、甲子園の魔物の正体です。
弱者を応援したいという観客心理

高校野球は部活動の一面であることも一つの理由です。
試合終盤になると、劣勢のチームを観客は応援したくなります。
甲子園といえど、高校生の部活動です。
負けているチームに「かわいそう」といった同情を抱きます。
その雰囲気が、勝っているチームをあたかも悪者かのようにしてしまいます。
選手たちは、四面楚歌のようにプレーをしなくてはならないのです。
ある選手がこんな言葉を残しています。

球場全体が敵のように見えた。(勝っているのは自分たちなのに)
5万人が敵のような状態でプレーすることはほとんど経験にないでしょう。
この観客の心理が、選手にプレッシャーを与えているのです。
投手の疲れ
試合終盤に逆転劇が多い理由は、
投手の疲れによるものがあります。
最近では、投手を複数枚そろえるチームも増えてきましたが、
まだまだエースに頼りきりのチームも多いです。
- 甲子園の真夏の暑さ
- 連戦による疲れ
- 慣れない球場、マウンド
- 大観衆でプレーする精神的プレッシャー
こういった理由で、試合終盤に崩れやすい条件がそろっています。
終盤になれば球威は落ちますし、コントロールも定まりません。
自然と死四球や真ん中への抜け球が増えやすいのです。
それゆえ、連打や死四球が増え、逆転劇が生まれやすいのです。
慣れない球場

常連校でない限り甲子園でプレーする機会は3年間で1度あるかないかです。
甲子園には、、
- 特有の浜風
- 以外に広いファールゾーン
- 特有の黒土
- 観客との距離感
- 歓声で声が届かない
といった普段とは違うフィールドでプレーしなくてはなりません。
↓甲子園球場の特徴、雰囲気、異空間を理解するには「ラストイニング」と「砂の栄冠」が非常にわかりやすいのでおすすめです。主もこれで高校野球を勉強しました↓
普段とは違う球場なので、ゴロのイレギュラー、フライの落球、打球との距離感といったエラーが起きやすい環境がそろっているのです。
エラーが絡めば当然ビックイニングにもなります。
それゆえエラー絡みの逆転劇が多いのです。
甲子園の魔物の正体まとめ
- 甲子園の魔物の正体はあの大観衆からくる精神的プレッシャー
- 連戦による投手の疲れ
- 慣れない球場故のエラーしやすい環境
- 高校生の精神的もろさ
観客の声援は意外にも選手に影響を与えています。
非科学的に見えてとんでもない影響力があるのです。
それだけでなく、連戦による心身の疲れ、慣れない球場などなど
科学的に見ても、ミスが起きやすい条件が甲子園球場にはそろっているのです。
近年の野球は、データやセイバーメトリクスばかりフォーカスされていますが、
それらには表れない隠れた部分にこそ、面白さがあるのです。
この記事が「甲子園の魔物」の理解につながれば幸いです。
それでは(@^^)/~~~


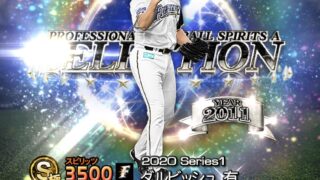







コメント