
侍ジャパンオリンピック金メダルおめでとう!!

日本の投手陣のすごさが際立つ大会だったね

メンバー的に打ち勝つ野球かと思ったけど、要所でバントや盗塁も絡めていたよね

初戦のドミニカ戦ではメルセデスに好投されて危ない試合もあったなあ

一発勝負の怖さ、難しさを実感したよね
柳田選手の故障でセンターがいない。
故障明けの千賀投手の選考。
源田選手がサード。
走れる選手がいない。
などなど様々な不安を抱えて始まった東京オリンピックですが、
蓋を開けてみたら5戦5勝のストレート勝ちでした。
今大会を観て、日本が今後どのように国際試合を戦うべきか筆者なりにまとめました。
スモールベースボールが原点にして頂点
今大会に選考を見る限り、打ち勝つ野球をしていくメンバー選考でした。
足の使える選手は源田選手くらい。
(山田選手も走れますが今年はまだ2桁盗塁もしていません)
しかし、終わってみたら5試合で9盗塁と積極的に足をからめた攻撃でした。
アメリカ戦の栗原選手のバントしかり2番に入った坂本選手も要所で送りバントも決めました。
ドミニカ戦の甲斐選手のセーフティースクイズも言わずもがなです。
ホームランもあれば小技もある。
これこそが日本が目指す野球スタイルではないかと思います。
そもそもスモールベースボールとは
野球における戦略の一つ。機動力や小技を特に重視する。対語はビッグベースボール
wikipediaより引用
第一回WBCの時、王監督が
「パワーやスピードは外国人選手には適わない。足や小技を絡めて攻めていく」
と言ったことで日本=スモールベースボールという認識が広まりました。
日本がスモールベースボールを目指す理由は
①国際試合では、4番をそろえても好投手にあたると打てない可能性がある
②外国人選手はクイックを得意としない
③外国人選手はカバーリングなどが雑(荒い野球をする)
①はドミニカ戦で誰もが痛感したでしょう。
絶好調の投手、しかも初見となると、簡単にホームランや連打は期待できません。
打線の奮起に期待してたら、気が付いたら試合が終わってしまいます。
シーズンは143試合と長いですので、たまたま1試合打線が沈黙しても、2試合目以降打線が爆発すればよいのです。
短期決戦では、そうもいきません。
打てなくてもバントや盗塁でランナーを進め、ヒット1本で点をとっていく野球スタイルが最適でしょう。
②は、メキシコ戦で露わになりました。
メキシコの選手はランナーが出てもクイックをしていませんでした。
そのためほぼフリーパスで走者2塁と形をつくれました。
走者2塁ならヒット1本で点を取れる可能性があります。
クイックが苦手な選手が多いため、走れる選手は必須です。
③に関しては、随所で見られました。
ドミニカ戦の最終回、柳田選手のファーストゴロが投手のカバーが遅れ内野安打になりました。
アメリカ戦の2点目は、山田選手が3塁を回ってもいないのに、バックホームをし失点しました。
外国の選手は、所々で雑な野球が目立ちました。
日本はその隙を逃さず攻めたことが、優勝につながったと言えるでしょう。
タイプの違う打者、選手を揃えろ
国際試合では、攻撃の選択肢、バッティングの選択肢が多いほど楽になります。
それが顕著に表れたのが、ドミニカ戦の近藤選手です。
最終回、2点ビハインド、一死一塁、この場面はなんとかつないでほしい場面です。
この場面の最低限の仕事は確実にヒットを打ち、アウトカウントを増やさずにつなぐことです。
(ホームランを打てば同点ですが、打ち損じをしゲッツーや内野フライは最悪です)
ここで、流し打ちも引っ張りもできる、ヒットを打つ確率の高いアベレージヒッターの近藤選手が代打に残っていました。
この試合のスタメンは、ホームラン打者が多く、低めにコントロールされたドミニカの投手に苦戦していました。
しかし、柔らかい打撃のできる近藤選手が、簡単にヒットを放ち1,3塁という最高の形をつくってくれました。(この大会の陰のMVPと言えるくらい価値があったと思います)
国際試合では、同じタイプのホームラン打者を並べるよりも、
流し打ちができる選手、左投手に強い選手、ホームランが打てる選手、ストレートに強い選手など、
タイプや特徴の違う選手をそろえることが有効です。
好投手にあたった際、同じタイプの打者が並んでしまうと、なす術なく終わってしまします。
コントロールのよいフォークボーラーは必須
アメリカでも活躍する投手のほどんどが制度の高いフォークボールを持っています。
(田中将大投手、前田健太投手、平野佳寿投手、野茂投手、大谷翔平投手etc)
「外国人選手はフォークボールが弱い」とよく言いますが半分正解で半分間違いです。
ではなぜフォークボールが有効なのでしょうか??
・人間の目は横の動きを捉えやすいが、縦(奥行)は捉えずらい
・日本にはフォークの文化が根付いている
という理由があります。
フォークの伝道師元中日・杉下さんを始め昔から、鋭く大きくフォークを投げる投手が日本には存在しました。
フォークを投げる文化が浸透していたのです。
そのため、日本はフォークを投げる人口が多い、かつ制度も高いため外国人選手は打てないのです。
(アメリカでは、フォークボールはデスピッチと呼ばれるなど敬遠されています)
今大会の千賀投手や栗林投手など制度の高いフォアボーラーは、国際試合では必須です。
極端なアンダーハンドが必要
稲葉監督は、青柳選手をアンダーハンドとして期待しているように見えました。
過去の国際試合では、渡辺俊介投手、牧田投手、高橋礼投手などアンダーハンドが躍動していました。
一発勝負の国際試合で、初見の投手、かつ下から投げる投手を打つとなると簡単にいきません。
しかし、彼らと青柳選手には大きな違いがあります。
それは、青柳選手は誰もが認めるアンダーハンドではないことです。
青柳選手は、サイドとアンダーの中間のクウォーターとも呼ばれています。
この中途半端さが、炎上につながってしまったのではないでしょうか?
アンダーハンドに求めるのは、慣れない球の軌道と珍しさです。
青柳選手は、サイドハンドとも見えますので、国際試合で活躍したアンダースローより、珍しさがなかったと思います。
アンダースローほど珍しくない球の軌道、かつ140キロそこそこのスピード感は、
外国人選手にとって打ちごろとなってしまったのでしょう。
そのため、各国とも簡単に仕留めることができたのではないでしょうか。
しかしアンダーハンドには注意点があります。
・慣れたらただの遅い球(130キロそこそこ)
・投げ逃げさせる(イニングを引っ張らない)
慣れたら終わりの手法なので、1巡や2巡ですぐ代える、
もしくは中継ぎのワンポイントで起用するのがマストでしょう。
国際試合の戦い方まとめ
- スモールベースボールを目指す
- タイプの違う打者、選手を揃える
- コントロールのよいフォークボーラーを集める
- 極端なアンダーハンドを投げ逃げさせる
これが日本の国際試合正しい戦い方です。
ほかにもコメント欄で意見おまちしております。
それでは(@^^)/~~~


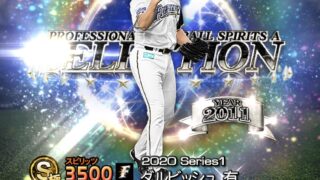




コメント